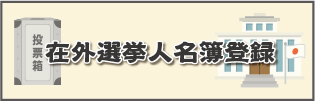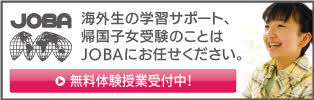英国の法制度
概要
歴史の古いイングランドの法制度は、民事法・刑事法とも、判決の積み重ねによる判例法と議会の制定する法令の2つの要素の組み合わせで構成されています。英国法のもとでは、過去の裁判の判例は単なる参考事例ではなく、それ自体がコモン・ローとして法律の効力を持つことが特色です。(同じ英国でもスコットランドと北アイルランドの法律は、会社法など一部の分野を除いて、一般に「English Law(英国法)」と呼ばれるイングランド・ウェールズ法とは大きく異なりますので注意が必要です。)
弁護士と裁判
英国の弁護士には、その大多数を占める、依頼者にサービスを提供するソリシタ―と、裁判手続きでソリシターを顧客として間接的な代理人の立場から法廷での弁論を担当する専門家である少数のバリスターの2種類があります。
ソリシターは、法的助言の他、契約書の作成・交渉、紛争のクレームや和解交渉などを役務とします。紛争が法廷で争われることになった場合には、ソリシターが弁論を専門とするバリスターを起用し、依頼者と連携しながらバリスターに指示を出します。
ソリシターはそれぞれ専門の分野を持っており、国際規模の投資案件や大型紛争を扱う「シティ・ファーム」から、知的財産や不動産、高額個人案件などに定評を持つ「ウェストエンド・ファーム」、地方の商業案件を扱う「リージョナル・ファーム」や、一般市民の不動産売買・離婚・相続・雇用問題や中小企業のビジネス案件を扱う街角の「ハイストリート・ファーム」までさまざまな種類があります。
バリスターは個人事業主としてチェンバーと呼ばれる共同事務所に所属し、担当する法律分野は、所属事務所ごとに専門化されています。
裁判所には請求額や事案の専門性に応じて、民事紛争では郡裁判所(County Court)、高等裁判所(High Court)、最高裁(Supreme Court)の他に、特化した商業裁判所・知的財産裁判所・労働裁判所・家族裁判所・不動産裁判所などがあります。刑事事件では治安判事裁判所(Magistrate Court)とより深刻な犯罪を扱う刑事法院(Crown Court)などが存在しています。
時間単位の報酬を基本とする英国の弁護士費用は、日本の弁護士費用と比較すると極めて高額になりがちです。報酬の単価は、弁護士の経歴と経験年数により左右されます。英国の訴訟では、ソリシターとバリスターを併用するために費用が倍増し、かつ敗訴した側が相手方の弁護士費用を負担する「敗者負担」の原則のもと費用リスクも大きいため、大多数の裁判が、弁護士費用が膨れ上がるトライアルの開始前に和解されています。
日本企業の英国進出
日本の企業が英国に現地法人や支店を開設する手続きは日本でのそれと比比較すると簡単であり、法律上、取締役の国籍や居住地が英国である必要もありません。しかし、当地の主要銀行が、株主の過半数が英国在住ではない、あるいは英国在住の取締役のいない中小企業による銀行口座の開設を認めないなどの実務上の難関があります。これに対して、既存の現地企業との合弁事業・資本提携やM&Aが迅速な進出を可能とします。
JV・資本提携やM&Aなどの進出方法では、デュー・ディリジェンス、契約交渉、条件付き合意から契約完了に至るまで、手続きの各段階において進出企業と受入企業それぞれが英国の弁護士を立てて調査や交渉を慎重に行います。
弁護士に依頼をするにあたり、世界の金融の中心地である英国では、各国の犯罪やテロ組織の資金洗浄が自国で行われることを防止するべく、近年では対マネロン(AML: Anti-Money Laundering)法がさらに厳重になり、疑わしい取引の報告義務を怠った場合には、弁護士・会計事務所を含め当地の企業や金融機関に禁錮刑を含む刑事罰が課されるとこともあるため、依頼企業は最終的なオーナーの身元や資金源の開示なども含む、年月を遡った厳格な情報開示(Know Your Customer: KYC)を求められます。
英国の法規のもとでの財務監査やコンプライアンスの要件は、日本に比べてより厳格であり、その基準を満たすのに小規模外国企業の拠点設立の予算を超えた費用が必要となり、事実上の参入障壁となるケースもあります。
企業活動の留意点
経済制裁措置:特定の国家、法人、個人を対象とする金融制裁(資産凍結や金融取引の制限)、貿易制裁(特定の国や事業体との貿易取引の禁止)、輸送制裁(航空・海運制裁を含む)などから成る英国政府の経済制裁措置は、広範にわたる上、常時変化しています。在英日系企業でも、違反をした場合には数百万ポンド規模の罰金もあり得る刑事罰や民事罰が課されますので、日頃からの注意が必要です。
雇用:2年を超えて勤続する従業員の解雇は、法に定められた業務上の必要性や懲戒解雇などの特定の条件に基づく場合を除き、不当解雇とされます。また、性別・人種・宗教・障害などを理由にしたハラスメントや、採用・昇進・給与の不平等などは、勤続年数に拘らず違法行為として損害賠償の対象となります。年間5.6週間分の有給休暇や産休育休・勤務時間の調整などの権利・疾病への対応に関する法律も日本と異なります。
入管:本社からの派遣を含め、英国居住権のない労働者を雇用するには、企業は政府に「スポンサー」として事前に認定・登録されていなければなりません。資格審査や就労状況のモニタリングの責任は、政府からスポンサー企業に転嫁されており、採用した労働者にビザ条件などの移民法の違反があった場合には、スポンサーは罰として資格剥奪などの処分を受けます。
労働資格チェック:スポンサー資格の有無に拘らず、英国内の全事業者には、 労働者が英国で就労する権利があることを、雇用を開始する前に確認する義務が課されており、これ怠ると罰金その他の法的な制裁が課されます。
その他:海外へのデータ転送の制限を含む個人データ保護法(GDPR)をはじめ、環境報告や監査を義務付ける環境保護関連法規、民間企業を対象とする贈収賄防止法、サプライチェーン上の第三国における労働力搾取や人身売買、強制労働などの調査・監視を義務付ける「現代奴隷制法」などの法律は、日本企業にとって特に注意の必要な法分野でしょう。
(協力:杉山英國法律事務所)
弁護士
Sugiyama & Co杉山英國法律事務所
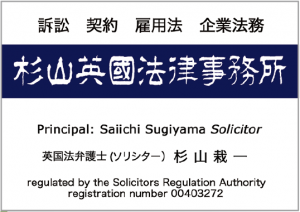
在英日本企業・邦人に良質の法役務を母国語で提供すべく、1988年よりLinklaters、Ashurstという大手事務所で日系金融機関、総合商社などの大型商業訴訟案件を15年に渡り手掛けたソリシター歴35年の杉山栽一が2004年に独立開業した事務所。2010年には元同僚の雇用訴訟advocate歴40年のベテラン、ロイ・カーロを迎え、両名の長年の実務経験に裏打ちされたアドバイスを提供する。
E enquiries
 sugiyama.co.uk
sugiyama.co.ukMeadow Lodge, Lobswood Manor, Surrey GU10 3RW
ビザ・コンサルタント
Immigration.UKイミグレーション.UK

就労許可、スポンサーライセンス、支社設立、ファミリービザ、永住権、学生ビザなどビザに関するさまざまなケースのコンサルティングおよびビザ取得代行を行う。ホームオフィスが推奨するSRA公認のアドバイザーが常勤し、最新の情報に基づいた的確なアドバイスによりビザ取得をサポート。日本語サービスもあり、気軽に相談できる。
T +81(0)3 6890 8578 (東京)
E ym
 immigration.uk
immigration.uk 会計事務所
P&Co LLPP&Co 会計事務所

P&Co会計事務所は、ロンドン・シティにて30年の経験と実績を積む、日系・アジア系企業を主な顧客層とするスペシャリスト集団。英国における会計全般、法人税務、個人税務、不動産投資、起業などについて日本語はもちろん英語でも相談できる。
E enq
 pcollp.com
pcollp.com18 Ensign St., London E1 8PA
シンクタンク
EBS (UK) Limitedヨーロッパ ビジネス サービス

1990年に英国法人としてロンドンで設立された独立系シンクタンク、EBS。創立時より政府機関や企業のための市場調査・コンサルティングに携わっており、欧州各国やEUの産業・経済・政策、社会制度などの委託調査を行う。分野は環境、エネルギー、AI、自動車、電機、電子、機械、食品など。会社設立から30数年、クライアントより高い評価と信頼を得て今日に至る。
E ebs
 ebsukltd.com
ebsukltd.com403 Canalot Studios, 222 Kensal Rd., London W10 5BN
就職・転職支援
JAC Recruitmentジェイ エー シー リクルートメント

1975年にロンドンで設立され、50周年を迎える老舗。欧州をはじめ日本(東証プライム市場上場)、米国、アジアに展開するグローバルな人材紹介会社。業界・職種に特化したコンサルタントが、その専門知識を活かし、最適な候補者と企業をつなぐ。まずは日本語で問い合わせを。
E uk
 jac-recruitment.co.uk
jac-recruitment.co.uk99 Bishopsgate, London EC2M 3XD

 Liverpool Street
Liverpool Street
ファイナンシャルアドバイス
Yasuto Arai Wealth ManagementYASUTO ARAIウェルスマネジメント

英国Chartered Financial Planner。個人向けには、資産形成・運用管理、私的年金、保険、相続税対策など、各ニーズに応じたファイナンシャルアドバイスを提供。また、企業向けには福利厚生・企業年金制度の設定をサポートする。
E yasuto.arai
 sjpp.co.uk
sjpp.co.uk 翻訳
Anglo-Japanese Translations Ltd.アングロジャパニーズ トランスレーションズ

在英35年を超えるディレクター自らが翻訳者、通訳者として蓄積した経験を活かし、300名以上の優秀な翻訳者、通訳者を欧州各地から集め、予算とニーズに合った迅速なサービスを提供。日英に限らず、欧州言語を通訳するベテランによる通訳をはじめ、翻訳、視察・観光ガイドなど、言語のプロによるビジネスサポート業務を行い、高い信頼を得ている。
E info
 anglo-japanese.com
anglo-japanese.com1 Bentley Close, London W7 3DL
生活サポート
One Stop Relocation Ltdワンストップ・リロケーション

英国の新生活立ち上げサポートとリロケーションサービス
◦イギリス全土をカバーし、すべて日本人スタッフが対応
◦駐在員に、赴任前後の数ヵ月にわたりコンシェルジュが対応
◦滞在期間中から帰任までトータルサポート
◦アウトソーシングによる総務担当の業務効率アップ
E info
 onestop-relocation.co.uk
onestop-relocation.co.ukEaling Cross, 85 Uxbridge Rd., London W5 5BW